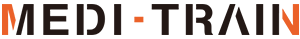デンマークの新興住宅地「Nye(ニュー)」を視察しました
9月9日〜9月12日に開催されたデンマークの視察ツアーレポートの第4弾。
4回目は、新興住宅地「Nye(ニュー)」です。
地域住民が中心となって運営し、対話と共創のまちづくりを行っている新興住宅地Nyeを視察しました。日本でも、人とのつながりに焦点を当てたまちづくりが注目されている中で、デンマークでのまちづくりについて視察してきました。
目次
オーフスの新興住宅地「Nye(ニュー)」
Nye地区は、デンマークの第2の都市オーフス郊外にある持続可能な都市開発を目指して計画された新しい住宅・コミュニティエリアです。自然との共生を前提にゼロから設計された、デンマークでも先進的な”まちづくりの実験場”ともいえる新興エリアです。
住民同士が関わりながら暮らしを作っていく仕組みや、環境配慮型の都市デザインが特徴です。その中にある「共同体の家」と呼ばれる場所は、地域住民のつながりを深めるための中核施設であり、イベント・対話・文化活動などが行われている空間です。
他にも、複数の住民ハウスや共有ハウス、小さな映画館、シェルター、文化農園など多様な交流拠点が設けられており、住民の主体的な活動を支えるインフラが整備されています。
Nye全体は段階的開発が進行中で、将来的には1万5000人、数百世帯規模の居住が予定されています。

写真奥に見えるのがオーフスの中心部

集合住宅とワークショップスペース
“人の動き”を軸にした都市デザイン
Nyeのまちづくりは、「人と人が自然に出会い、対話が生まれる」ということを大切にして設計されています。
まず印象的だったのは、道をあえて真っすぐにしない設計です。直線の方が移動は早いかもしれませんが、Nyeでは蛇行する道や丸みを帯びた道が多く、人がふと立ち止まったり、花壇に目を留めたり、小さな会話が生まれたりするように工夫されています。街そのものが“対話を生む仕掛け”としてデザインされていました。
さらに、入り口のカフェ兼スーパーも交流を生むようにデザインされた設計でした。仕事から帰ってきて家に直行するのではなく、「ちょっと寄り道して今日の出来事を話して帰る」ような流れを自然に促す場所です。特にお母さんたちが集まり、談笑する姿も見られ、ここがコミュニティ形成の大切なハブになっていることを感じました。
そして、公共空間には“心理的安全性(ヒュッゲ)”を意識した設計が様々な場所にされています。教会や遊び場、屋外ワークスペース、花壇などが生活動線に沿って配置され、歩くだけで人と出会い、景色に心が動き、五感がやさしく刺激されるような街並みです。
Nyeのまちづくりは、ただ住むための建物を並べるのではなく、人の暮らしと心の動きを丁寧に見つめながらデザインされていました。

入口にあるカフェで談笑するお母さんたち

歩道の側には花壇があり自然豊かな環境
住民とともにつくり、暮らしの中で育つ“支え合いのまち”
Nyeのまちづくりは、企業が一方的に完成形を提示するのではなく、住民と企業が一緒になって育てていく“共創型”のスタイルが特徴です。運営する民間企業 Tækker Group は、「みんなと話し合って、孤立しないまちづくりを目指す」ことをテーマに、開発の初期段階から住む予定の人々や専門家を招き、「どんなまちをつくりたいか」を率直に語り合うワークショップを重ねてきました。そのベースにあるのは、 “Trop on(トロップ・オン)” ~互いに支え合い、孤立しない価値観~。
ここでは、まちを“与えられるもの”ではなく、住民自身が日々の暮らしを通して形づくっていくという姿勢があります。
街路や花壇にはユニバーサルデザインが取り入れられ、木箱で高さを出すことで、高齢者や身体が不自由な人でも自然に植物に触れられるよう工夫されています。どんな住民でも、花壇や公共空間を通じてまちづくりに参加できるような環境が整えられていました。
また、住民が不要になった物を自由に置き、必要としている人が持ち帰れるリユーススペースも設置されています。物を通じてゆるやかに交流が生まれ、自然なコミュニティ形成を後押ししているようでした。
Nyeは、単なる“街”をつくるのではなく、住む人が互いに支え合いながら暮らしを育てていく“関係のデザイン”を大切にしている場所なのだと感じました。

手入れをする人へ配慮した高さのある花壇

住民が利用できるリユーススペース
多様な人が暮らせる仕組みづくり”
Nyeの住宅は、大きさや価格帯、賃貸・買取などのバリエーションが幅広く、若者から高齢者、低所得層から高所得層まで、多様な人が住めるように設計されています。コミュニティを特定の属性に偏らせず、異なる背景を持つ人たちが自然に交わりながら暮らすことができるよう、工夫がされています。
高齢ご夫婦が語る“第二の人生”
視察時には、Nyeに移住した高齢のご夫婦のお宅にも訪問しました。
手作りリンゴジュースとお菓子で温かく迎えてくださり、デンマークの文化を実感できるひとときでした。
ご夫婦は以前、別の地域で静かに老後を過ごしていたものの、人との関わりが少なく、どこか寂しさを感じていたそうです。そんな時にNyeを知り、思い切って移住されたとのこと。ここでは散歩を楽しむだけで自然に住民と挨拶を交わし、子どもたちとの触れ合いも増え、Nyeでの暮らしは楽しく満足していると語っていました。
また、一般的にシニアハウジング(高齢者住宅)は「人生の終わり」と考えられることが多いけれども、Nyeは「新しい人生の始まり」です、と表現されていたのがとても印象的でした。
高齢者住宅も安心や安全などを考えられて設計されており、住居としては整っていると思います。しかし、このご夫婦の言葉から、人々の暮らしは住居というハードだけではなく、人とのつながりや交流といったソフトもいかに大事であるか、ということを改めて感じました。

お伺いしたご夫婦のご自宅での素敵なおもてなし
Nyeが示す未来のまちのヒント

Nyeは、単なる新興住宅地ではなく、「人が人として豊かに暮らすための環境をつくる」ことに真正面から向き合った、非常に丁寧なまちづくりが行われている場所でした。
特に心に残ったのは、家そのものだけでなく 家と家の“間”の空間まで丁寧にデザインしていること、そして人の動きを観察しながら都市を形づくっている姿勢 です。また、さまざまな世帯や所得層を受け入れる多様な住まいの設計、住民主体で進むボトムアップ型のまちづくり、そして自然と対話の生まれる環境づくりも印象的でした。
Nyeを歩いていると、五感がほどよく刺激され、暮らしそのものが「リハビリ」になっていくような感覚さえ覚えます。無理に何かを“やる”のではなく、生活の動線の中で気づけば体も心も動いている、そんな環境がここにはありました。
住宅という“ハード”だけではなく、人とのつながりや関係性という“ソフト”が同じくらい大切に扱われているからこそ、人が安心して暮らせる。
その実践例を目の前にした思いでした。
今回の視察は、日本の地域づくり、福祉、そして子育て支援のあり方を考える上でも、多くのヒントを与えてくれる貴重な機会となりました。
前の記事へ
次の記事へ