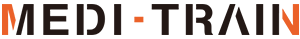オフグリッド型エコビレッジ「グロブンド」を視察しました

9月9日〜9月12日に開催されたデンマークの視察ツアーレポートの第3弾。
3回目は、オフグリッド型エコビレッジ「グロブンド」です。
デンマークの第2の都市オーフスの郊外にある、オフグリッドを目指すエコビレッジ型コミュニティとして開発途中であるGrobund(グロブンド)を視察しました。
目次
Grobund(グロブンド)とは
デンマークの第2の都市オーフスからバスで約1時間半ほどにあるEbeltoft郊外に位置する、オフグリッドを目指すエコビレッジ型コミュニティです。廃工場を中心に、タイニーハウス、工房、農園、共用スペースを組み合わせた持続可能な生活実験を進めています。環境負荷を最小限に抑えた、サステナブルな暮らしと生産を両立させる共同体として、”ゼロウェイスト” と”オフグリッド””借金のない暮らし”を 理念に、持続可能な社会モデルを実践しています。
Grobundの構成について
グロブンドの敷地は、「住む」「仕事をする」「カルチャー」の3つのセクションに分かれています。
まず「住む」セクションでは、1世帯あたり約150㎡の土地が割り当てられ、それぞれが自分たちでタイニーハウスなどを建てて暮らす予定です。今後、約120世帯がこの地に移住してくる見込みです。
次に「カルチャー」セクションには、ピザ屋やアイスクリーム屋、カフェなどがあり、地域の人や観光客など外部の人も利用できるようになっています。ここは、住民と外部の人々との自然な交流を生み出す場として機能しています。

敷地内にあるピザ屋

コミュニティスペース
「仕事」とコミュニティ運営
3つ目の「仕事をする」セクションは、グロブンドの始まりの場所でもある廃工場を再利用した工房です。2018年にこの工場を買い取り、仕事と生活を共にする“生活共同体”としてスタートしました。工房に入るには、入会金として日本円で約120万円を支払い、共同で働くというコンセプトに賛同することが条件です。
現在、この工房には54の民間企業が入居しており、約150人が働いています。太陽熱発電やきのこの生産、タイニーハウスの製作など、幅広い分野の小規模企業が集まり、それぞれが責任を持って運営に関わっています。また、プラスチックの使用をできるだけ避け、自然素材を積極的に取り入れるなど、環境への配慮も徹底されています。

廃工場を改装した工房

工房で作成されるタイニーハウス。販売もしている。
持たない・捨てない・分かち合う-グロブンドが目指すソーシャルサスティナブルな社会
グロブンドでは、大切にしている3つのコンセプトがあります。
1つ目は「借金がないこと」、2つ目は「ゴミがないこと」、3つ目は「リソースを平等に分けること」です。
「借金がないこと」とは、借金を返すために朝から晩まで働くような生活では、持続可能で豊かな人生は送れないという考えに基づいています。借金をせず無理のない暮らしの中で、自分の時間と心のゆとりを大切にすることがサステナブルだとしています。
また、「ゴミがないこと」「リソースを平等に分けること」は、大量生産・大量消費の社会から離れ、必要なものを分け合い、できるだけモノを持たずに暮らすという価値観を表しています。
こうした理念のもと、グロブンドは助け合い・支え合いを基本とした共同組合形式で運営され、資本主義に依存しない“ソーシャルサスティナブル”な生活を実践しています。
彼らはこの生き方を「発信する」のではなく、「現地で体験してもらう」ことを重視しており、今後1〜2年で完成を予定しているこのプロジェクトの姿を、ぜひ現地で見てほしいと語っていました。
”お互い様”がつくる持続可能な暮らし

案内してくれたエマさんと視察メンバーでの集合写真
今回は、廃工場を拠点に、タイニーハウス・農園・工房・コミュニティスペースを組み合わせ、環境負荷を最小限に抑えながら、暮らしと仕事の両立を目指すサステナブルな共同体「グロブンド」を視察しました。ここでは、住民一人ひとりが責任を持ち、”お互い様”という相互扶助の精神のもと、民主的に運営する共同組合形式の生活が実践されています。
日本でも馴染みのある“お互い様”という文化が、この地では持続可能な暮らしの仕組みとして息づいており、人と人とのつながりを大切にしながら、脱資本主義で暮らす在り方を信じ実践している彼らの考え方とライフスタイルを学ばせていただきました。
グロブンドのような共同組合形式の在り方は、これからの社会や地域づくりのヒントになると感じました。
前の記事へ