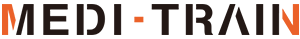男性の育休取得に向けて準備すること

2022、2023年にかけて施行、改正された「育児・介護休業法」により、近年では男性も育休を取得し、家庭の時間を増やすという傾向に変化しつつあります。法改正に伴い、さらに男性育休への注目が高まっています。
しかし、何も準備をしないままでは、ただ休みを取るだけで終わってしまう可能性も少なくないのではないかと感じています。そこで今回は、男性の育休取得に向けて準備することをお伝えします。
目次
男性育休の心構え、取得する際に気をつけるべきこと
男性の育児休業取得率は年々増加しており、厚生労働省の調査結果によると2022年で13.97%まで上昇しています。
私自身が産婦人科クリニックで勤務していることもあり、男性の育休が増えてきていることは肌で感じています。
ただ、冒頭にもお伝えしましたが、女性側からの視点では「男性はただ育休を取ればいいというわけではない」ということをよく耳にします。
元々、料理や掃除などの家事ができる、女性への気遣いができる、そのような方は育休取得後にも家事・育児参画ができると思います。
それに加えて、女性の心と身体の変化について理解し、寄り添うことができれば完璧です。もちろん、最初から完璧な方はいないので、男性育休を取る前からの準備が大切になってきます。
イライラモヤモヤ育休にしないために目的と役割を明確に
男性の育休を考えるときに大切なのは、取得の目的とやること(役割)を明確にすることです。
まずは「出産直後のママをケアする」「ママと家事・育児をシェアする」「ママの職場復帰と入れ替わりで家事・育児を担当する」といった育休の目的と、それに沿った取得時期や期間を決めましょう。その上で、男性は育休中に何をするのか、自分の役割を具体的にイメージしてみてください。
何をしたら良いかわからない場合は、ぜひ奥様に何をサポートしたら育児を一緒に頑張れそうか、聞いてみてください。夫婦で対話する時間をたくさん設けてみてください。
産前産後の正しい知識を身につけよう

大切なパートナーに寄り添うために、妊娠から出産、産後に心と身体がどのように変化するのかを知り、理解することがとても大切になります。
産後うつについて
産後1年以内の母親の死亡原因で一番多いのは「自殺」です。
産後うつの発症率は10~15%と言われており、決して珍しいものではありません。誰しもなる可能性がある病なのです。
産後うつがもっとも発症しやすいとされている時期は、産後3ヶ月以内と言われており、この期間に男性が育児に積極的に参加することは、産後うつの発症を予防するうえでも大切です。
特に、夜間の赤ちゃんのお世話をパパが担当するなど、ママがしっかりと睡眠時間を確保できる工夫ができると良いです。産後うつの原因のひとつは、産後のホルモンバランスの変化と言われています。どんなにパパが積極的に育児に参加していても発症してしまうことはあります。
だからこそ、産後うつについて正しい知識を持ち、パートナーに異変が見られたときに、1人で抱え込まず、すぐに適切な機関へ相談、連携することもパパの役割です。
産院や保健センターで行われているパパママ教室に参加する
男性の妊婦体験や抱っこ・沐浴練習など、今この瞬間しか体験できない時間を夫婦で一緒に体感できることは、産後に力を合わせて育児をしていくために必要です。
女性は、自分の身体の変化と赤ちゃんの命、両方と向き合い続けており、妊娠期〜産後はとても不安定な時期になります。
1人ではなく、隣に一緒に向き合ってくれる1番の味方がいることがどれだけ心強いことかはかり知れません。ママが抱く安心感が、赤ちゃんへの愛情として届きます。
余談ですが、産前産後の期間、旦那さんがどれだけ協力的であったかは、熟年離婚率に影響を与えるという報告もあります。
男性はいつ頑張るのか?産休を取ると決めた、今この瞬間からスタートです。
まとめ
まだまだ全ての方が男性育休を取得できる制度が整っているわけではありませんが、たとえ休みが取れなかったとしても、できることはたくさんあります。
夫婦で一緒に悩みながら育児に取り組むこと、赤ちゃんと一緒に成長していけること。親として、こんなにも幸せなことはないのではないかなと感じています。皆さまが楽しみながら子育てしていただけることを願っています。
前の記事へ
次の記事へ