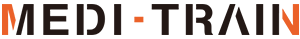妊活に向けて知っておきたいこと③~妊娠した時のための準備編~

今回は、妊娠に備えて知っておきたい「妊娠した時のための準備」についてお伝えします。初めて妊娠したママはもちろん、パパも参考にしてみてください。
目次
妊娠はどうやってわかる?
妊娠の確認には、市販の妊娠検査薬を使います。妊娠検査薬は、ドラッグストアや薬局で購入できます。
月経予定日より1週間経っても月経が来なければ、妊娠検査薬を使用してみてください。もしも排卵が遅れていた場合には、このタイミングでも陰性になることが考えられます。1回目に陰性であっても、1週間後に再度検査をしてみてください。
妊娠がわかったらすること
ここからは、妊娠がわかったらすることを紹介します。
産婦人科を受診しましょう
妊娠検査薬で陽性を確認したら、月経予定日の1~2週間頃に産婦人科を受診しましょう。
妊娠検査薬だけでは正常妊娠かどうかは分かりません。子宮外妊娠ではなく、ちゃんと子宮内に妊娠しているかを確認する必要があります。
母子健康手帳をもらいましょう
母子健康手帳とは、法律に基づいて交付されるお母さんと赤ちゃんの健康管理を記録する手帳で、住民票のある自治体の役所などで交付を受けます。
病院で妊娠していることが確認できればいつでも受け取ることができますが、実際には、赤ちゃんの心拍が確認できた頃に「母子手帳をもらってきてくださいね」と、病院から指示されることが多いです。また、母子健康手帳は日本語だけでなく外国語版もあります。
出産場所の選び方
「どこで産むか」ということは、大切な検討事項です。ここでは、出産場所や産後の育児環境について解説します。
どこの施設で産むか
「どこで産むか?」は、比較的早い段階で決める必要があります。分娩予約は、妊娠20週までという施設もあれば、妊娠10週にはもう予約がいっぱいになる施設もあり、施設によって状況は異なります。妊娠10週頃というと、ちょうどつわりのピーク。体調が悪いなかでの日々の生活や仕事に加え、大事な分娩施設選びをするのは結構大変です。
妊活中から候補となる施設をピックアップし、情報を整理しておくと、妊婦のあなたはきっと過去の自分に感謝したくなるでしょう。
分娩施設を決めるにあたり、ポイントとなる次の視点について、妊活中から2人で話し合っておきましょう。
- 里帰り出産―当然ながら、里帰りするかどうかで施設選びは大きく変わります。里帰り出産をする場合は、里帰りするまでの間に妊婦健診を受ける近隣の施設を探します。
- どのような出産をしたいか―出産の主役は、あなたたちご家族です。新しい家族をどのように迎えたいか、出産にあたり最も大切にしたいことは何か・・・そんな話からはじめてみましょう。具体的には「安全第一、とにかく設備や体制が万全であることを優先したい」「無痛分娩がしたい」「おいしい食事が出るところがいい」「立ち合い出産をしたい」など、希望を挙げてみましょう。
- 産後の育児環境-産後の育児はどのような環境で行いますか。例えば、両親は遠方で近くには子育てを手伝ってくれる人がいないという場合には、入院中になるべく赤ちゃんのお世話の練習ができるといいですね。そうすると、赤ちゃんとお母さんが一緒に過ごすスタイルの施設で、スタッフからの指導が手厚い所だと安心です。さらに、退院後に産後ケアまで受けられる施設だと安心です。または、夫の帰宅が遅いので、ほぼワンオペ育児で上の子含め3人の育児をします!というママは、入院中は育児の練習よりもしっかり休んで体力回復に努めた方がよさそうです。となると、赤ちゃんを預けて休めるスタイルや、無痛分娩で出産の消耗を抑えるのも手かもしれません。このように、産後の育児環境もポイントの一つです。
出生前診断について
出生前診断は、妊娠中にお腹の赤ちゃんの病気や健康状態について調べる検査です。
出生前診断にはいくつかの種類があり、それぞれ検査する時期、結果が出るまでの時間、精度、費用などが違います。また、すべての先天性疾患(生まれつきの病気)について調べられるわけではありません。
出生前診断についての詳しい説明はここでは割愛しますが、もし検査を希望する場合は、比較的早い週数での検査になるので、これについても妊活の段階で2人で考えを整理しておけると良いでしょう。
検査の種類や特徴について下調べをしておき、妊娠が分かったら受診した婦人科で早めに申し出て相談しましょう。
まとめ
いかがでしたか。もちろん、事前に準備や話し合いをしていても順調に進むことばかりではありませんし「まさか」という、予想外の出来事もあるでしょう。
しかし「どのような出産にしたいか」を話し合うことは「どういう子育てがしたいか」「どういう家族になりたいか」に通じるものがあり、話し合うこと自体に大きな意義があります。時には意見がぶつかったり、パートナーや自分の新たな一面に気づき、不安になったりすることもあるでしょう。そうした価値観のすり合わせが、すでに子育てのスタートなのです。
前の記事へ
次の記事へ