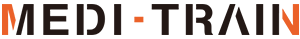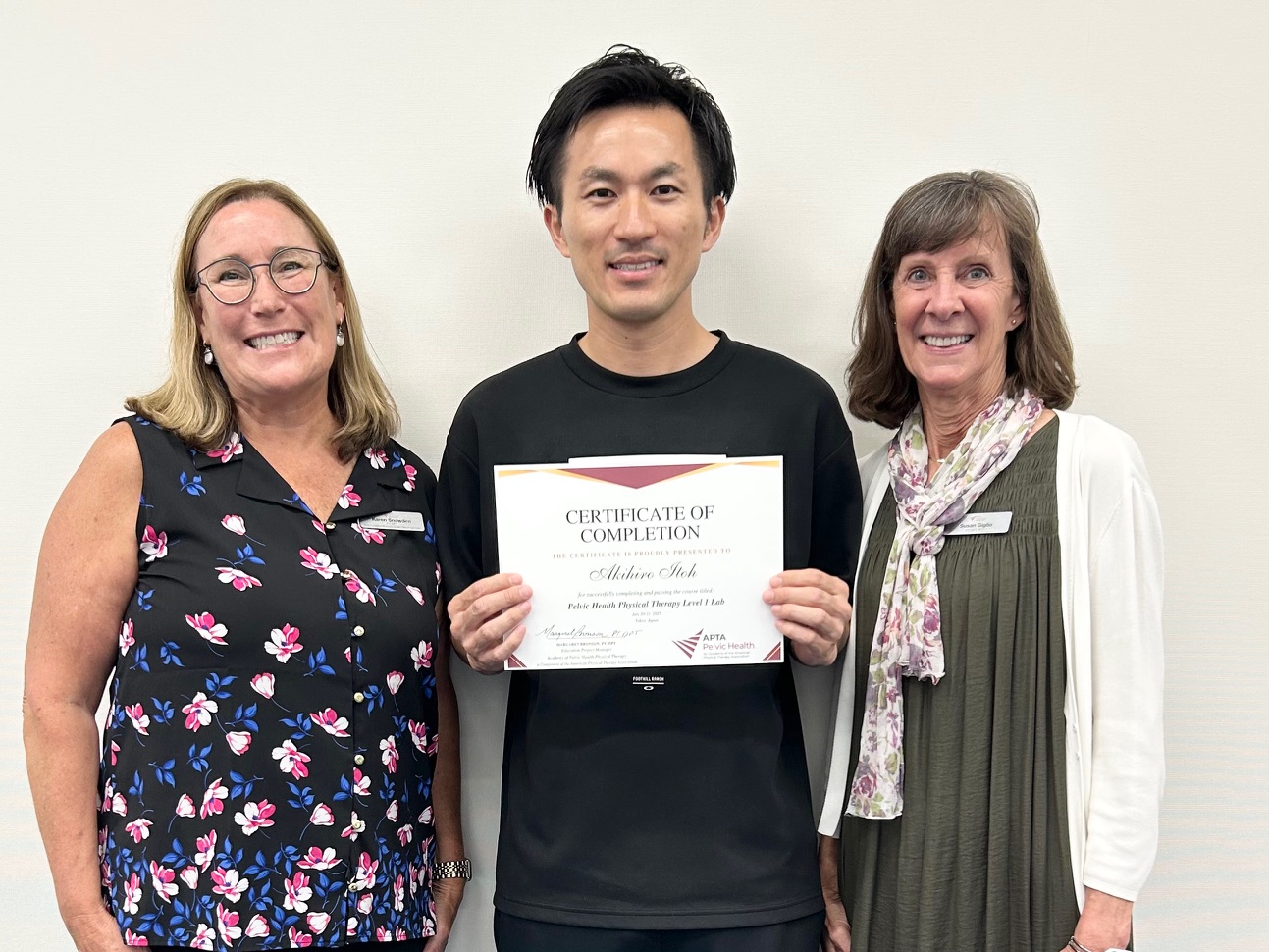デンマークデザイン&福祉視察ツアーに参加してきました
9月9日〜9月12日に開催されたデンマークの視察ツアーに参加してきました。
風と地と木合同会社の宮田尚幸さん主催で、パッシブハウス・ジャパンの建築家の方々と一緒に視察しました。
今回の視察ツアーは、「福祉の本質を支える”人”と”場”の在り方を探り、心豊かで持続可能な共生社会のヒントを得る」というテーマで、様々な場所を視察しました。
その中でも印象に残っているものを中心に皆さんにお伝えしたいと思います。
本記事から4回にわたり連載する予定です。続編もぜひご覧ください。
第1回目の今回は、「エグモントホイスコーレンとインクルーシブ」です。
今回の視察では、エグモントホイスコーレンとエグモントホイスコーレンの卒業生で、地域に住む重度の身体障がいをお持ちの方のご自宅に伺いました。
目次
エグモントホイスコーレンとは

エグモントホイスコーレン(Egmont Højskolen)は、障がいのある人もない人も、共に暮らし、学び合うことができる、全寮制のフォルケホイスコーレン(民衆学校)。学歴・年齢・障害の有無を問わず、多様な背景を持つ人が「人生を豊かにする学び」と「自立的な生活」を体験する場として設立されました。「尊厳」「連帯」「自己決定」を教育方針に掲げており、全校生徒の約半数近くが障がいを持つ生徒。「障がい当事者が介助者を採用し、費用は出身地の自治体が支払う」というデンマークの制度が利用されており、残り半数の生徒はアシスタント(介助者)として雇われながら勉強しています。
≪フォルケホイスコーレン≫
フォルケホイスコーレンとは、デンマーク発祥の成人教育機関です。テストや成績はなく、18歳以上であれば年齢国籍関係なく誰でも入学でき、学生は寄宿し共同生活をしながら学びます。学べる内容は、スポーツや工芸、デザイン、哲学など多岐にわたり、「生きた対話」を重視するのが特徴です。その思想の基礎を築いたのはN.F.S.グルントヴィで、彼は暗記中心の教育を批判し、「人間同士の対話による相互の人格形成」を提唱しました。フォルケホイスコーレンでは、知識の習得だけでなく、対話を通して自分を知り、人として成長することが重視されています。
エグモントホイスコーレン(以降エグモント)では校内外に、障がいがあっても様々なことに挑戦できる環境が整備されていました。体育館では、リフトに吊られボルダリングに挑戦する生徒、海岸では車椅子ごと海に降りて向かいの島までセーリングすることも。リスクに配慮しながらも、誰もが平等に挑戦も失敗もできる環境になっています。

楽しそうに過ごしている生徒たち

リフトが整備され車椅子ユーザーもボルダリングに挑戦できる

車椅子ユーザーも利用できるウォータースライダー

リフトを使用し車椅子ごと乗船できるボート
校内を見学させていただいて、生徒たちの生き生きした笑顔や楽しそうな雰囲気が印象的でした。他のホイスコーレも見学したことのある参加者の方も、エグモントは「別格」と表現されていました。他のホイスコーレともまた一線を画していて、本当の意味で障がい者と健常者が共存・共生している学び場であるということが、自分と向き合いながら自分自身の福祉観を育むとても素晴らしい環境だと思いました。
エグモントで見つけた自分らしい暮らし
エグモントの卒業生で、障がいがありながらも地域で暮らしている方の自宅に伺いました。自宅はバリアフリーで、リフトや寝返り補助装置などノーリフティングケアを実践し、介助者の負担軽減にも配慮されている環境になっていました。
この方はエグモントに在籍後、デンマークのパーソナルアシスタント制度を利用して複数の介護士を雇い、一人暮らしをしています。彼は「人生で一番激しかったが充実していた」とエグモントでの日々を振り返り、家族に頼っていた生活から、自分のことを自分で行う全寮制の環境に大きな変化を感じたそうです。現在の自立した暮らしは、エグモントで自分に必要な支援や理想の生活を見つめ直した経験が大きく影響しているのではないかと感じました。

エグモント卒業生のシリウスさんと

室内にはリフトが設置されている
こうしたフォルケホイスコーレンの存在や地域での障がい者の暮らしなどの背景には、やはり社会保障制度の充実があります。
そして、そのデンマークの充実した社会保障の背景には、高い税負担があります。消費税25%、所得税50%と国民の租税負担率は約70%ですが、その代わりに世界最高水準の福祉を享受できる制度が整っています。国民は、高負担を受け入れ、国家を信頼して納税しています。
こうした社会保障制度の充実やフォルケホイスコーレンの存在、国としての成り立ちや文化など、様々な背景が現在の高福祉国家デンマークに結びついています。
インクルーシブな社会の実現とは
今回、エグモントをアテンドしてくださったのが、片岡豊さん。
高校卒業後にデンマークへ渡り、フォルケホイスコーレンを経験。日本人として初めてエグモントの教員を務め、日本人留学生受け入れの道を開いたパイオニアとなる方です。
そんな片岡さんから学んだ印象的なことを紹介します。
”誰のため?主語は誰?”
高齢者福祉の3原則(生活の継続性・自己決定の尊重・残存能力の活用)について話をしていた時、「その主語は誰?それはあなたが“させたい”ことではないの?」と言われたことが、とても印象に残りました。
私たちは「生活を続けさせたい」「自己決定させたい」と考えがちですが、それは支援者側の思いであり、必ずしも本人の望みとは限りません。本当に大切なのは、“目の前の人が何を望んでいるのか”を丁寧に考えることだと改めて気づかされました。
インクルーシブは自分から
さらに印象的だったのが、「インクルーシブは自分が入らないとインクルーシブにはならないよ、自分が中心だよ」という言葉です。
インクルーシブとは、「全てを包括する、包み込む」という意味から、障がいの有無、性別、国籍、年齢、その他の多様な背景を持つ人々を分け隔てなく受け入れ、共生していく考え方です。
インクルーシブというと、社会全体が目指す理想のように感じていましたが、実は“自分がどう関わるか”から始まるものだと気づかされました。自分も社会の一員であり、誰かに影響を与え、また影響を受けながら生きています。インクルーシブとは、誰かを包み込むだけでなく、自分自身もその輪の中にいるということ。
そして、その考え方を理屈ではなく、日々の生活の中で自然と体感できる場所がエグモントなのだと思いました。
これから
この視察を通して、障がい者と健常者を分けない在り方というものを短い時間でしたが体感させていただきました。インクルーシブや共生するということは、理屈ではなく、実際に現地で生き生きした笑顔や楽しそうにしている姿を見たり体験したりすることで、本当の意味での理解につながるのではないかと感じました。
また、フォルケホイスコーレンというものを通して、「人と比べない」という考え方を大切にしたいと思いました。
自分は何が好きなのか、何がしたいのか、どう生きていくのか、ということは誰から決められるものではなく、自分で決めていくという在り方は、スポトレなどで関わる子ども達にも伝えていきたいと思います。
最後に、エグモントホイスコーレンで貴重な学びの機会を与えていただいた、エグモントホイスコーレンの元教員・片岡さん、アテンドしていただいた宮田さんに心より感謝致します。
前の記事へ
次の記事へ